買い物をするたびに消費税を払っていると思っていた。
社会保障費に使うためのお金ならしょうがない、なんて思っていた事もあった。
でも実際は、私は消費税を払っていなかった。
消費税は間接税ではない
税制上は、消費税は間接税とは定義されていない。「企業が消費者から消費税を集めて納めろ」ということは消費税法には一言も書いていないのである。つまり、消費者は消費税を払っていない。企業が消費税を売上から計算して支払っているだけだ。
もし消費税を消費者が収めているというのであれば、それは会社が払っている法人税や所得税も消費者が収めているというのと同じだ。
我々消費者はコストとして、小売価格に転嫁されている消費税分の金額を間接的に負担はしている。だが、消費者は国に消費税を納めているとは言えないだろう。
レシートにかかれている消費税相当額というのは、「この金額分、商品の価格を値上げしていますよ」、という表示であるというだけで、この金額が消費税として国庫に納税されているという意味ではない。
そして、価格というのは需要と供給のバランスで決まるものなので、値上げ分のコストが消費者に受け入れられなければ商品は売れず、店側は値下げをして売ることになる。
つまり、物の価格に消費税が乗っかっているわけではなく、価格には他の税金や人件費、仕入れ値などと一緒になって消費税もコストとして売値の価格に含まれているだけということがわかる。
レシートの消費税額は意味がない?
もしレシートにこの消費税相当額の金額が書いてあってもなくてもコストとしては負担しなければいけないので、レシートに書かれている消費税額は意味がない数字だと言えなくもない。
一方、自分で商売をしている場合は、物やサービスを買うときに消費税相当分とレシートに書いてあるのは一応意味があるとも言える。
購入した物やサービスを使って、新しい付加価値(物やサービス)を提供する場合は、レシートに記載された消費税分を課税仕入れとして控除できる。
しかし、この金額表示がなくても会計上仕入れ値の10/110が控除対象と計算すべきものなので、やはりレシートの数字には意味がないとも言えそうだ。
消費税がいかに悪税であるか
そもそも中曽根内閣の時、「売上税」として導入しようとしたものを、「消費税」と名前を変えて消費者が消費税を払っていると錯覚させることで、金がないところからも税金を集められるようにしたのが消費税なのである。
会社が赤字でも消費税を納めなければならないと言うことはかなり問題だろう。常識的に考えて、お金がないところから税金を取るということは税制上あってはならない。
そもそも消費に税金をかけるということは消費を抑える効果があるので、好景気によるデマンドプルインフレの状況でない状況では、時限的にでも消費税は下げなければならないと思う。
また、輸出還付金の問題もある。これはフランスで輸出企業に補助金を出すために導入された付加価値税と同じ仕組みだ。これは輸出にかかる消費税は0%と計算することで、逆に還付金を受け取れる制度になっているのだ。
経団連が消費税を19%まで上げろなどとのたまうのは、輸出の売上があればその分補助金がもらえるからだ。円高で苦しかった時代では一定の効果と納得感があったかもしれないが、現在の円安を考えれば輸出大企業への補助金などはもういらないだろう。
以上のことを勘案すると、消費税は悪税である。急いで正常な経済を取り戻すため税制の見直しをしてほしい。
蛇足:なぜ消費税がおかしいことに気がついたのか
なぜ消費税がおかしい、ということに気がついたのか。一応残しておこう。
私が所属している会社ではECサイトを運営していて、私はそのシステム開発を担当している。
消費税計算をどうするかという部分で、消費税は「消費者が払ってるんだから、当然外税計算だろう」と開発を進めていたのだが、商品ごとに外税を計算するやり方ただと、複数の商品を同時に購入した際に金額に端数が生じてしまうことがあり、なんでだよと思いつつもどのような仕組みにするべきか悩んでいた。
色々と調べた結果、国税庁のHPで消費税の計算の仕方を見つけた。
※ 仕入税額の積上げ計算の方法として、課税仕入れの都度、課税仕入れに係る支払対価の額に10/110(軽減税率の対象となる場合は8/108)を乗じて算出した金額(1円未満の端数が生じたときは、端数を切捨て又は四捨五入します。)を仮払消費税額とし、帳簿に記載(計上)している場合は、その金額の合計額に78/100を掛けて算出する方法も認められます(帳簿積上げ計算)。
要は売上に10/110をかけた数字が消費税だということなのだが、これは消費税が売上に対して9.09%かかるということだ。
ここでは消費税の10%という数字がどこにも出てこないことに違和感を覚えたのだが、(軽減税率が導入される前だったので8%についてはまだ意識していなかった)とりあえずそういう計算でよいということで、商品の税込み金額の合計金額に10/110をかけて消費税を再計算することでECサイトのシステム開発の方ははうまく乗り越えられた。
しばらくしてから、会計の知識も付けておいたほうが良いかもなと思い立ち、簿記3級のテキストで勉強を始めた。当然、消費税計算のところでは外税で計算しているので商品ごとに消費税を計算していた場合、先に述べた端数の問題が起きるなというところでまた引っかかってしまった。
やはりなんか変だなと思い、YoutubeやWebで消費税のことを片っ端から調べまくった。すると森井じゅんさんが消費税について解説している動画を見つけたのだ。
この動画を見て、ものすごくびっくりした。
なんと、消費税は間接税ではない、というのだ。そんな事あるはずがないだろう。
会計でも外税計算しているし、レシートにも消費税として記載されている。学校でも間接税だと習った気がする。
今勉強している簿記のテキストと全然違うし、今まで消費税を払っていたのに、急に払っていないと言われても理解が追いつかなかった。
何いってんだこの人、とその時は思った。
いやでもまてよ・・・どっちかが間違っているなら、どちらが正しいのか、もうちょっと調べて自分で納得したかった。
そしてYoutubeで消費税について解説している動画を鬼のように片っ端から見まくり(多分200本ぐらいは見た)、三橋貴明さんや藤井聡さんなどの解説で裁判の判決や消費税法には消費者という言葉が一切出てこない、という説明ですべてが納得できた。
消費税は間接税ではなく、国民を騙して導入された悪税だということを。


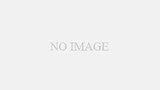
コメント